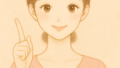はじめに
同居嫁にとって、お盆や正月は避けられない大イベント。
普段は静かな家も、この数日間だけは“人の波”でごった返します。
お墓参りや仏壇の準備といった伝統的な行事に加え、親戚の出迎え、食事の支度、子どもの世話…。
「休み」どころか、むしろフル稼働で動き回る日々です。
今年のお盆も例外なく、いや、むしろ例年以上に大変でした…。
今日は、そのリアルな体験を少し詳しく記録しておきたいと思います。
義母は跡取り、親戚はとにかく大人数
私の義母は3人きょうだいの長女で跡取り。
下には妹と弟がいて、3人とも仲が良いため、お盆や正月には必ず全員が集まります。
単純にきょうだいだけなら3人。
でもそこに配偶者、その子ども、さらに孫まで…。
さらに旦那も3兄弟なので、それぞれの家族も集まります。
気づけば、総勢30人ほどの大所帯。
親戚が顔を合わせて仲良くしてくれること自体はありがたいことです。
でも、迎える立場からすると「準備・片付け・気配り」で体力も気力も削られてしまいます。
家が一気に“親戚テーマパーク”のようになり、落ち着く暇がありません。
夏のお盆はプールとカオス状態
夏のお盆は、庭に子ども用プールを出すのが恒例になっています。
子どもたちは大喜びで遊びますが、そのあとの対応が大変。
- 濡れたまま家の中に突入して、床がびしょびしょ
- 「喉乾いた〜!」と飲み物の注文ラッシュ
- 親たちはおしゃべりに夢中で、子どもは放置気味
私はずっと走り回り、飲み物を出したり、タオルを配ったり、床を拭いたり…。
子どもはかわいいけれど、責任を感じてしまう分、気疲れは限界です。
本来なら「自分の子は自分で見てね」と言いたいところ。
でも、義母の目や周囲の空気を考えると、なかなか強く言えず…。
結局、気を遣うのは私ばかりになってしまいます。
滞在時間が長い、そして追い打ちが…
「お盆の集まり=ちょっと顔出して帰る」なんて理想ですが、現実は真逆。
朝11時頃にやって来て、帰るのは16時過ぎ。
ようやく帰った…と思ったら、甥っ子が「もっと遊びたい!」と居残り宣言。
結局その子だけ夜まで滞在し、親は「じゃあ遊んでる間にデパート行ってくる」と自由行動。
私はその間もずっと対応し続ける羽目に。
同居嫁の「休日」なんて存在しないんだな、と痛感します。
「ごめんね」が建前すぎて腹が立つ
みんな最後に口をそろえて「いつもごめんね〜」と言います。
でも、その“ごめんね”に本気を感じたことは一度もありません。
本当に申し訳ないと思っていたら、
「お線香だけあげて早めに帰るね」とか、
「子どもが迷惑かける前に帰ろうね」とか、行動に出るはず。
正直、あの建前の一言が一番疲れる…。
私だったら、気を遣わせないためにも短時間で済ませます。
同居嫁のお盆に必要なのは「割り切り」
今年改めて感じたのは、同居嫁がお盆を乗り切るには 割り切りが必要 だということです。
- 完璧にこなそうとしない
- 親戚の言葉を真に受けすぎない
- できることとできないことを線引きする
そうしないと、心も体も持ちません。
「本家に嫁いだ以上、仕方ない」ではなく、「自分のペースでやれる範囲だけやる」と思った方がずっとラクです。
まとめ
今年のお盆も、体力も気力も消耗する数日間でした。
「ごめんね」と口では言いながら、自由に振る舞う親戚たち。
本家に嫁いだ以上、避けられない現実ではあるけれど、やっぱりモヤモヤは残ります。
それでも、子どもたちの笑顔や家族のつながりを感じる瞬間もあるのも事実。
疲れた気持ちと同時に、「これが“同居のお盆”なんだな」と受け入れる気持ちも少しずつ芽生えています。
同じように“お盆でぐったり”している同居嫁さん、全国にきっといるはず。
この記事が少しでも共感や励ましになればうれしいです。
#同居嫁
#義母
#お盆